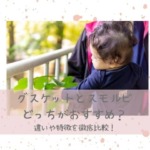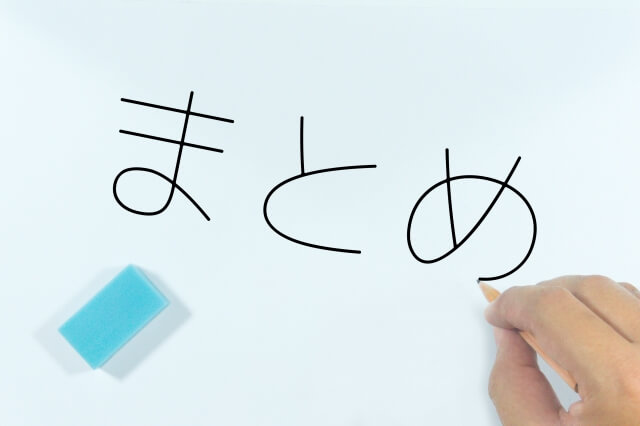保育園に入園が決まると、意外と持ち物リストが多いことにびっくりしますよね。
その一つがお昼寝布団!
保育園で使うお昼寝布団は、できれば安く済ませたいと考える人もいるかもしれませんね。
「どこで買うのが一番お得?」
「やっぱりデザインにもこだわりたい!」
「おすすめのお昼寝布団はある?」
など、初めての入園だとわからないことも多いですよね。
ここでは、お昼寝布団をどこで買うか迷っている人のために、おすすめのショップやアイテムをたっぷりご紹介します!
ぜひ参考にしてみてくださいね。
保育園のお昼寝布団はどこで買う?
保育園で使うお昼寝布団はどこで買うのがおすすめなのか知りたい!という人も多いはず。
ここでは、お昼寝布団を買える場所を5つご紹介します。
バースデイ
しまむらグループ発のベビー&キッズ用品専門店「バースデイ」。
リーズナブルな価格とかわいいデザインが人気で、お昼寝布団も豊富にそろっていますよ。
店舗によって取り扱っているアイテムが異なりますが、敷布団や掛布団など数点がセットになっているものはもちろん、敷布団のみ・掛布団のみでも販売されています。
西松屋
ベビー服・子供服・マタニティ服の専門店「西松屋」も、お昼寝布団を購入するのにおすすめのショップです。
リーズナブルな価格のセットからちょっと高級なアイテムまで、幅広く取り扱っているのが魅力。
西松屋はオンラインショップでもお昼寝布団を購入できます。
インターネットで注文してお店で受け取ることもできますよ。
しまむら
ベビー・子ども向けの専門店ではありませんが、「しまむら」でもお昼寝布団を取り扱っています。
「バースデイ」に比べると取り扱い数が少ないケースがありますが、バースデイ同様リーズナブルな価格でお昼寝布団を購入できますよ。
タオルケットやハーフサイズの毛布なども充実しているので、シーンに合わせて買い足したいというときにも便利です。
ニトリ
シンプルで長く使えるお昼寝布団が欲しいなら「ニトリ」がおすすめ!
お昼寝布団というと、ピンクや黄色、青などカラフルなカラーバリエーションが中心ですが、ニトリのお昼寝布団はベージュやグレーなど、比較的落ち着いた色味がそろっているのが特徴です。
ニトリは季節に合わせた商品が充実しているので、夏はタオルケット、冬はブランケットなどを買い合わせてもいいかもしれませんね。
楽天
いろいろなアイテムを見比べてから購入したいと考えている人は、楽天市場がおすすめです。
メーカーやブランドで絞ってもいいですし、予算に合わせて検索することもできるのはうれしいですよね。
同じ商品でもショップによって価格が異なることもあるので、よりお得に購入できるのも魅力の一つです
保育園のお昼寝布団【人気おすすめセット】
保育園で使うお昼寝布団をどこで買うか迷っている人も多いはず。
ここでは、人気のおすすめセットについてご紹介します。
un doudou お昼寝布団7点セット
敷布団、掛布団、枕にそれぞれのカバーが付いていて、さらに持ち運びに便利なバッグの7点がセットになった、まさに保育園のお昼寝布団にぴったりのアイテム。
子どもが喜びそうな6種類のデザインから、好みのアイテムを選べますよ。
カバーはもちろん、布団本体もまるごと洗えるのもうれしいポイント。
そしてカバーは綿100%なので、肌が敏感な子どもでも安心して使えそうです。
SANDESICA(サンデシカ) 全部洗えるお昼寝布団6点セット
しっかり硬めのベビー向け式布団と、2歳頃からの子どもにおすすめのふんわりやわらかい敷布団の2種類から選べるお昼寝布団5点セット。
敷布団と掛布団にそれぞれのカバーと防水バッグがセットになっていて、必要最低限のものだけで良いという人におすすめです。
デザインも4種類あり、好みに合わせて選べますよ。
もちろんカバーも本体も、洗濯機で丸洗い可能です。
Babyshower(ベビーシャワー) お昼寝布団7点セット(園児用)
持ち運びに便利なバッグを含む、保育園のお昼寝に必要な7点がセットになったアイテム。
届いたら洗わずにすぐに使えるよう、オゾン除菌を施した状態でお届けしてくれるのが魅力の商品です。
性別に関わらず使いやすいナチュラルなデザインがそろっていて、どれを選ぼうか迷ってしまうほど。
シンプルなデザインが好きな人におすすめです。
PUPPAPUPO(プッパプーポ) 洗えるお昼寝布団5点セット
敷布団と掛布団、それぞれのカバーとバッグがセットになったお昼寝布団。
子どもの肌に直接触れるカバーには、ふんわりやわらかい綿100%の天竺ニットを採用し、肌触りにこだわっています。
お昼寝用の敷布団は薄いものが多いイメージですが、こちらのアイテムはしっかり厚みがあり寝心地も抜群!
バッグは撥水加工が施されているので、雨の日でも布団を濡らさずに持ち運べます。
エムール お昼寝布団5点セット
シックでナチュラルな北欧風のデザインのお昼寝布団を探している人におすすめなのが、こちらのバッグ付き5点セット!
敷布団は手洗いならOKというアイテムが多いなか、こちらの敷布団は洗濯機で丸洗いが可能なんです。
カバーはもちろん綿100%で、肌あたりが優しいのも特徴。
バッグは上部のみにファスナーがついているタイプと、サイドまでファスナーがついているタイプの2種類から選べます。
西川 お昼寝布団7点セット
やっぱりお布団といえば西川!
保育園のお昼寝といえど子どもが毎日使うものなので、品質にこだわりたいという人におすすめのアイテムです。
すべて家庭で洗える仕様で、カバーは速乾タイプというのも魅力の一つ。
また、カバーは子どもが大好きなサンリオやアンパンマンなどのキャラクターのデザインがそろっていますよ。
10mois(ディモワ) Hoppetta(ホッペッタ)おひるねふとんセット
おしゃれなデザインが人気の「10mois(ディモワ)」。
お昼寝布団もかわいさとナチュラルな雰囲気をたっぷり感じられる、おしゃれなデザインが魅力です。
保育園のお昼寝に必要な敷布団と掛布団、それぞれのカバーがセットになっています。
バッグもナチュラルテイストのかわいいデザインなのがうれしいポイント。
HashkuDe(ハッシュクード) 洗える2重ガーゼ布団7点セット
保育園を卒業するまで長く使えそうな、シンプルなデザインが魅力のお昼寝布団7点セット。
色はグレー・ピンク・ブルーの3種類から選べます。
カバーに使用している生地はエアフローという特殊加工が施され、とろけるようなやわらかさを実現しました。
洗濯をするたびに風合いが良くなるので、一般的なガーゼとはまた違った肌触りを実感できますよ。
保育園のお昼寝布団【敷布団のみ】
保育園によっては、敷布団だけ持ってくるように指示があることもあるようです。
また、掛布団は手持ちのもので十分というご家庭もありますよね。
ここでは、敷布団だけ欲しいという人のために、おすすめの敷布団をご紹介します。
6歳までの寝具図鑑こどものふとん ベビーマットレス しっかりベビー敷布団
お昼寝用の敷布団は、持ち運びをしやすいようにやや薄めに設計されているアイテムも多いです。
こちらのアイテムは約6.5cmのしっかりとした厚みが特徴で、寝心地の良さは抜群!
赤ちゃんでも安心して寝かせられる硬さなので、0歳から入園する予定の子どもにもおすすめです。
抗菌・防臭・防ダニ加工も施されているため、衛生面が気になるという人にもぴったりですね。
HashkuDe(ハッシュクード) お昼寝 洗えるヌード敷ふとん
ベビー期から幼児期まで長く使える敷布団を探している人におすすめなのが、こちらのヌード敷布団。
厚さ2.5cmなのでとにかく軽量で、持ち運びしやすいのも魅力の一つですね。
敷布団は丸洗いできないものも多いですが、コンパクトに畳んで洗濯機で丸洗いできます。
価格もリーズナブルなので、洗い替え用に買い足したいという人にもぴったり。
西川 お昼寝敷き布団
お昼寝用の敷布団も品質にこだわりたいなら、やっぱり西川がおすすめ。
しっかり硬めの中綿を採用し、赤ちゃんでも安心して寝かせられる設計になっています。
耐久性がありへたりにくいので、入園してから卒園まで長く使えるのも魅力です。
手洗い可能なので、敷布団も清潔なものを持たせたいという人におすすめです。
保育園のお昼寝布団を選ぶポイント
保育園のお昼寝布団を買う際、どのようなポイントを押さえて選べばいいか気になりますよね。
まずは、保育園からのお知らせをチェックして、必要なものとサイズを把握しておきましょう。
それを踏まえて、
- 敷布団の硬さ
- 敷布団・掛布団の重さ
- 家庭で洗濯できるか
- 持ち運び用バッグが付いているか
- 布団やカバーの素材
- カバーのデザイン
などを重視して選ぶのがポイントです。
カバーだけでなく、敷布団や掛布団本体も家庭で洗濯ができるものがおすすめ。
また、カバーの洗い替えを一緒に購入できるとうれしいですね。
保育園のお昼寝布団はどこで買う?まとめ

お昼寝布団を用意してくれる保育園もありますが、多くの園ではお昼寝布団を持参するケースがほとんど。
お昼寝布団を販売しているお店は意外と多く、バースデイや西松屋など子ども服専門店はもちろん、ニトリやしまむらでも購入することができます。
また、なかなか出かけられないという人は、楽天やAmazonなどのネットショッピングを利用するのもおすすめ。
どこで買うか迷っているなら、ぜひネットショッピングも活用してみてくださいね。
7点セットや5点セット、敷布団単品など用途に合わせて、お気に入りのお昼寝布団を見つけましょう!